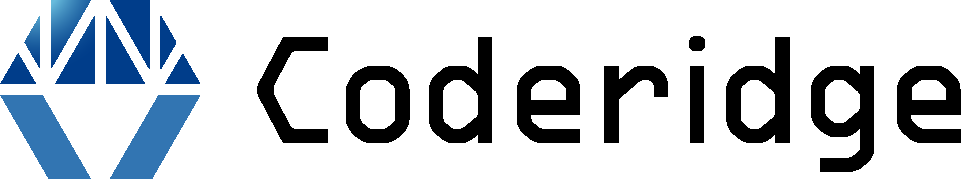企業の早期選考とは?早期選考がある企業の探し方5選や注意点を徹底解説

「周りの友人が内定をもらい始めて焦っている」「早期選考って聞くけど何をすればいいの?」そのような不安を感じている経済学部や理系の学生も多いはずです。
早期選考は就活を有利に進めるチャンスですが、準備不足のまま挑むと逆効果になることもあります。
この記事では、早期選考の基礎知識から実施企業の探し方、注意点までを詳しく解説します。
初めての就職活動でも安心して臨めるよう、選考の全体像と対策を整理しておきましょう。
▼「自分のスキルが活かせる内定直結インターンを探したい…」
『コードリッジ(coderidge)』は、インターンに繋がる”無料”WEBエンジニア養成プログラミング!
まずはLINEで詳しく話を聞いてみる!登録はこちらから!
企業の早期選考とは
企業の早期選考とは、本選考のスケジュールよりも前倒しで実施される選考活動を指します。
多くはインターンシップやイベントに参加した学生を対象に、限られた枠でおこなわれるのが特徴です。
就活の本番前に内定を得られるチャンスでもあり、近年では実施企業が急増しているため、まずは以下の早期選考に関する基本を押さえておきましょう。
- 早期選考と本選考の違い
- 早期選考のスケジュール
- 早期選考を実施している主な業界
早期選考と本選考の違い
早期選考は、本選考よりも前倒しで始まる非公開または限定的な選考ルートのことを指します。
一方、本選考は就活解禁後に広く学生を対象におこなわれる正式な採用活動です。
早期選考は、インターンシップ参加者やリクルーターと接点のある学生を対象とすることが多く、少人数かつ短期間で進行します。企業によっては、早期選考を通じて内定を出すケースもあり、就活全体を有利に進めることが可能です。
ただし、本選考よりも準備期間が短く、事前に自己分析や業界研究を済ませておく必要があります。早期選考に落ちた場合、本選考に応募できない企業もあるため、エントリー前に情報収集が不可欠です。
早期選考は「内定直結ルート」ともいわれる一方で、戦略的な準備が求められるため、慎重な判断が必要です。
早期選考のスケジュール
早期選考は大学3年生の夏から冬にかけておこなわれることが多く、特に夏や秋のインターンシップ終了後に本格化します。
たとえば6月から8月にかけて夏季インターンが実施され、その後、9月から11月頃にかけて企業の人事担当やリクルーターからの個別接触が開始。10月から翌年1月にかけて、実際の選考がスタートし、エントリーシートの提出や適性検査、面接などがおこなわれます。
早ければ2月から3月の時点で内々定が出ることもあり、就活解禁よりもはるかに早いタイミングで結果が出るといった特徴を持ちます。
このようなスケジュールのため、インターンの段階からすでに就活が始まっているという意識を持ち、夏前には企業研究や自己分析、ES対策を進めておくのが理想です。
特に人気企業はこの流れで採用をほぼ完了させることもあるため、スピード感のある対応が求められます。
早期選考を実施している主な業界
早期選考を積極的に取り入れている業界は、外資系企業、大手IT企業、金融機関、総合商社、そして一部のメーカーなどが挙げられます。
外資系企業では特に投資銀行や戦略コンサルティングファームが代表的で、選考時期が早く、大学3年生の夏には面接が始まっているケースも少なくありません。
一方、大手のIT企業やメーカーではインターンを通じて選抜した学生に対し、秋から冬にかけて早期選考を実施する傾向があります。
ここでは、インターンでの評価がそのまま選考に直結し、早い段階での内々定に結びつくことも。金融業界や商社も同様に、限られた優秀な学生を早期に囲い込む目的でこの制度を活用しています。
こうした業界ではインターン参加が早期選考の前提となる場合もあるため、早めの行動と情報収集が成功につながります。
企業が早期選考をする理由3つ
企業が早期選考をおこなう背景には、単なる人材確保にとどまらず、採用活動全体の質と効率を高めたいという明確な狙いがあります。
特に人気企業や大手企業ほど、優秀な学生にいち早くアプローチし、他社に先んじて囲い込むために早期選考を導入しているのです。
ここでは企業側が早期選考を実施する代表的な3つの理由について解説します。
- 優秀な人材を確保するため
- 選考フローを効率よく進めるため
- 志望度の高さを判断するため
優秀な人材を確保するため
企業が早期選考を実施する大きな理由の一つが、優秀な人材を他社に先駆けて確保することです。
学生の多くは限られた期間で複数社に応募するため、タイミング次第では他社の内定を先に受けてしまい、優れた人材を取り逃がすリスクがあります。
そのため、優秀な学生と早い段階で接点を持ち、インターンや説明会を経て関係性を築いたうえで、早期に内定を提示するケースが増えています。
特に外資系企業や大手企業など競争が激しい業界では、「早い者勝ち」の側面が強く、企業側は夏のインターン直後から選考を始めることも少なくありません。こうした背景から、学生の質を見極めつつ、早めに採用を決定する流れが一般化しつつあります。
企業にとっては、採用計画どおりに人材を確保することが採用成功の鍵であり、早期選考はそのための有効な手段となっています。
選考フローを効率よく進めるため
早期選考の導入には、選考フロー全体の効率化という目的もあります。
通常の本選考では数千人規模のエントリーがある場合もあり、すべての学生に対応するには多大な時間とコストがかかります。
そこで、あらかじめインターンやイベントなどを通じて接点を持った学生に絞って選考を進めることで、選考プロセスを簡略化し、採用活動をスムーズに進められるのです。
また、早期選考を通じて内定を出せば、本選考での採用枠を絞れるため、人事担当者の業務負担を軽減することにもつながります。早期選考を通じて全体の3〜4割の内定を確定させる企業もあり、選考の質とスピードのバランスをとるうえで重要な役割を果たしています。
効率的な人材獲得を重視する企業にとって、早期選考は単なる早さではなく、戦略的な手段と位置付けられているのです。
志望度の高さを判断するため
早期選考は、学生の志望度をより正確に見極める手段としても活用されています。
早期に企業と接点を持ち、積極的にインターンや説明会に参加する学生は、他の応募者と比べてその企業への関心が高い傾向にあります。企業側は、こうした行動を通じて「本当にうちで働きたいのか」を評価材料として活用しているのです。
選考期間が限られている早期選考では、応募のハードルがやや高くなるため、本気でその企業を志望している学生しか参加しづらいという面もあります。このことが逆に、企業にとっては「選考に来た=志望度が高い」という判断基準になりやすいのです。
また、選考の場面だけでなく、エントリーシートの記述や面接での受け答えにも志望動機の強さが表れます。企業はそうした要素から、将来長く働いてくれそうな人材かを見極め、ミスマッチのない採用につなげようとしています。
早期選考がある企業の探し方5選
早期選考を実施している企業は年々増加していますが、一般に公表されていないケースも多く、自分で積極的に情報収集をおこなう必要があります。
ここでは、早期選考に参加できる企業を効率よく見つけるための具体的な方法を5つ紹介します。
- 就活サイト
- リクルーター面談
- OB・OG訪問
- イベントや説明会
- インターンシップ
就活を有利に進めたい学生は、これらの方法を早い段階から実践しておくと大きな差につながります。
就活サイト
早期選考の情報を得るうえで、まず活用すべきなのが就活サイトです。
リクナビやマイナビ、ONE CAREER、外資就活ドットコムなどの大手サイトでは、企業ごとの選考スケジュールやインターン情報が掲載されています。中には、「早期選考あり」といった記載がある企業ページもあり、エントリーの判断材料になります。
また、サイトに登録しておくとプロフィールや志望業界に応じて企業からスカウトメールが届くことも。こうしたスカウトは、通常選考よりも優遇される特別ルートであることも多く、早期選考への第一歩として有効です。
特に競争率の高い企業では一般公開されていない情報を得られる場合もあるため、複数のサイトに登録し、こまめにチェックする習慣をつけておくとよいでしょう。
リクルーター面談
リクルーター面談は、企業の人事や若手社員が学生に直接アプローチしておこなう非公開型の選考ルートです。早期選考を狙ううえで重要な手段のひとつといえます。
リクルーターから連絡が来た学生は、すでに企業から「注目している存在」として見られていることが多く、特別ルートでの選考につながるケースも少なくありません。
リクルーター面談は、インターン参加者やOB・OG訪問を通じて接点ができた学生に対しておこなわれるのが一般的です。就活サイトのスカウト経由で企業が面談をオファーしてくる場合もあります。
このように、リクルーター面談は表立って募集されない分、学生側からのアクションが重要になります。インターンや企業イベントで積極的に話しかけ、印象に残ることで指名を受ける可能性が高まるでしょう。
OB・OG訪問
OB・OG訪問は、実際にその企業で働いている先輩と直接話すことで、内部の情報や選考の傾向を知ることが可能な貴重な手段です。
特に早期選考を実施している企業は表向きに公表していないことも多く、内部の人との接点を持つことで初めて知ることもあります。
訪問時には、企業の文化や仕事内容だけでなく、以下のような質問を自然に織り交ぜることで、選考ルートの存在や対策のヒントを得られます。
- 早期選考はありますか?
- どのような学生が呼ばれやすいですか?
OB・OGとのつながりが強くなると、その方から人事に推薦してもらえる可能性もあり、思わぬ形で早期選考に呼ばれることもあります。
大学のキャリアセンターやSNS、就活支援アプリを活用し、積極的にアポイントを取りましょう。
イベントや説明会
企業主催のイベントや説明会も、早期選考に招待されるきっかけとして有効な手段です。
多くの企業は、学生の行動力や志望度を図るために、説明会での参加態度や質問内容を細かく見ています。その結果、特に印象のよかった学生には、その場で個別選考の案内がされることもあるのです。
一部の企業では「選考直結型説明会」と称して、エントリーシートの提出や一次面接が含まれるプログラムを開催しているケースもあります。このようなイベントに参加すれば、一般的なルートよりも早く選考が進み、内定に近づく可能性が高まります。
イベント情報は就活サイトだけでなく、大学のキャリアセンターや公式SNS、メールマガジンなどにも掲載されるため、定期的にチェックすることが大切です。気になる企業があれば、公式サイトから情報をこまめに収集しましょう。
インターンシップ
インターンシップは、早期選考の入り口として重要な手段のひとつです。
企業はインターンを通じて学生のスキルや人柄を見極め、評価が高ければインターン終了後に早期選考へ案内することが多くなっています。特に長期インターンや実務型インターンでは、実際の仕事に近い内容を体験できるため、企業とのマッチング度が高まりやすいです。
また、社員とのコミュニケーションの中で志望度や積極性を示せるため、選考につながる可能性がより高くなるでしょう。
「インターン参加者限定の選考会」や「インターンから本選考スキップ」といった形で早期内定を出す企業も増えており、参加しておくだけで有利な立場に立てる場合があります。
意欲のある学生ほど、インターンの段階から本気で取り組んでいます。
早期選考を受ける際の注意点3つ
早期選考は内定獲得のチャンスを早めに得られる反面、事前準備や選考後の対応を誤るとデメリットも生じかねません。
特に、本選考とは異なる制限やルールが存在するため、注意点を理解しておくことが重要です。
この章では、早期選考を受ける際に学生が特に気をつけるべき3つのポイントを解説します。
- 準備不足にならないように注意が必要
- 早期選考で落ちた企業には本選考でエントリーできない可能性がある
- 内定保留期間は事前に確認しておく
準備不足にならないように注意が必要
早期選考は一般的な本選考よりも前倒しでおこなわれるため、準備期間が短くなりがちです。
エントリーシートや面接対策、自己分析、業界研究などを十分におこなっていない状態で臨むと、本来の実力が発揮できず、不本意な結果になってしまうこともあります。
特に夏のインターン後すぐに早期選考に突入する企業も多く、早ければ大学3年生の9月〜10月に選考が始まることもあります。早期選考を意識するのであれば、大学3年生の春から準備をスタートしておくのが理想です。
また、複数企業のインターンやイベントに参加していると企業研究が浅くなりやすく、志望動機があいまいとなり面接で落とされるリスクも高まります。
早期だからこそ、限られた時間の中でもしっかりと準備を整えて臨むことが、成功への第一歩となります。
早期選考で落ちた企業には本選考でエントリーできない可能性がある
企業によっては、早期選考で不合格になった学生を本選考では再度受け入れないという方針をとっている場合があります。
これは企業側が「すでに評価を終えた学生」として処理するケースであり、再エントリー不可、あるいは選考免除の対象外となることもあります。
そのため、準備不足のまま早期選考に応募してしまうと、本来は本選考で通過できた可能性のある企業の門を自ら閉ざしてしまうことになりかねません。特に志望度の高い企業に対しては、応募のタイミングや自身の準備状況を慎重に判断することが求められます。
早期選考に参加する前には、その企業が「本選考との併願を許可しているか」「早期不合格後に再チャレンジが可能か」といった情報を事前に確認しておくことが重要です。
内定保留期間は事前に確認しておく
早期選考で内定を獲得した場合、企業から早めの返答を求められることがあります。
通常の本選考であれば、複数社の選考結果を見比べて進路を決める余裕があります。一方、早期内定では保留期間が短く設定されていることも多いため、他社選考との兼ね合いで悩むケースが少なくありません。
特に、第一志望ではない企業から早期内定をもらった際に、「キープしたいものの返答期限が迫っている」といった状況に陥ることもあります。返答を遅らせることで印象が悪くなる可能性もあり、選考辞退や内定辞退のタイミングにも気を配る必要があります。
こうしたリスクを避けるためにも、内定が出る前に企業の保留期間について調べておくことが大切です。また、必要に応じて正直に相談する姿勢も重要であり、誠意を持って対応すれば理解を得られるケースもあります。
『コードリッジ(coderidge)』なら早期選考につながるインターンシップを紹介できる
早期選考につながる有効な手段のひとつが、実践的なインターンシップへの参加です。
なかでも、IT業界や技術職を志望する経済学部・理系学生におすすめなのが、『コードリッジ(coderidge)』のインターン紹介サービスです。
『コードリッジ(coderidge)』は、エンジニアとして即戦力レベルを目指す新卒と、実践力ある人材と企業をマッチングする新しい就活支援サイトとして機能しています。
未経験者向けに設計された独自プログラムでは、現役エンジニアが学習と実務の両面をサポート。開発現場に近い実践的なスキルが効率的に身につけられるのが特長です。
このように、実務に即したスキルを備えた学生は企業からの評価が高く、インターン終了後に早期選考や内定へとつながる可能性も大いにあります。
就職活動を有利に進めたい方は、ぜひ『コードリッジ(coderidge)』を活用して、企業との接点をいち早く築いてください。
▼「自分のスキルが活かせる内定直結インターンを探したい…」
『コードリッジ(coderidge)』は、インターンに繋がる”無料”WEBエンジニア養成プログラミング!
まずはLINEで詳しく話を聞いてみる!登録はこちらから!
まとめ
早期選考は、就活をスムーズに進める大きなチャンスです。
タイミングよく情報収集し、インターンやイベントを通じて企業との接点を持てば、内定獲得も現実的になります。
ただし、早期であるがゆえの注意点や準備不足によるリスクもあるため、冷静かつ計画的に取り組むことが大切です。
自分に合った方法で行動し、納得のいくキャリアの第一歩を踏み出しましょう。
▼「自分のスキルが活かせる内定直結インターンを探したい…」
『コードリッジ(coderidge)』は、インターンに繋がる”無料”WEBエンジニア養成プログラミング!
まずはLINEで詳しく話を聞いてみる!登録はこちらから!
大学からプログラミングを始めるなら、
コードリッジ!
空き時間に完全無料でエンジニアに。
まずはLINE登録!
この記事を読んだあなたにおすすめ
記事を検索
まずはLINE登録!体験講座情報も!
LINE登録へ