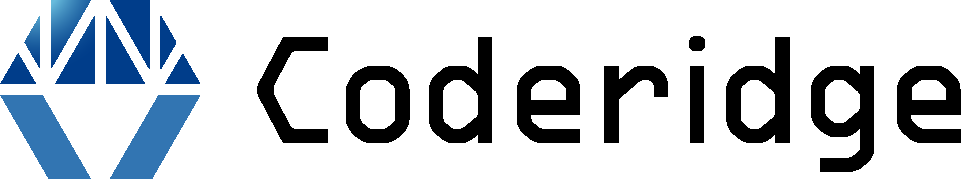「インターンシップって具体的にどんなことをするの?」「企業側はどうやって企画すればいいのかわからない…」
そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
インターンシップは、学生にとっては実務に触れる貴重な体験の場であり、企業にとっては将来の人材と出会う重要な機会です。
しかし、内容や目的が曖昧なまま実施してしまうと、学生からの評価が低くなったり、採用活動に結びつかない結果となってしまう可能性もあります。
この記事では、インターンシップで実際におこなわれている内容やタイプ、実施期間ごとの例、学生にとって印象に残るプログラム内容、さらには企業が企画する際に押さえておくべきポイントまで、総合的に解説します。
これからインターンシップを企画したい企業の方、効果的に実施したい人事担当者にとって役立つ情報をお届けします。
▼「自分のスキルが活かせる内定直結インターンを探したい…」
『コードリッジ(coderidge)』は、インターンに繋がる”無料”WEBエンジニア養成プログラミング!
まずはLINEで詳しく話を聞いてみる!登録はこちらから!
インターンシップとは
インターンシップとは、学生が企業で一定期間働くことで、実際の業務内容や企業文化を体験する制度です。
職場の雰囲気を知ったり、自分の適性を見極めたりするための重要な機会であり、企業にとっては自社に合う人材との接点を築く場でもあります。
インターンシップで実施される内容は、業界説明や職場見学から実務体験、グループワークまで多岐にわたります。
期間や目的に応じて内容は大きく変わり、採用直結型のプログラムも増えているのです。
インターンシップは何年生から参加できるのか
インターンシップは大学3年生の夏から本格化するイメージが強いですが、実際には1年生や2年生から参加できるプログラムも増えています。
特に文部科学省の推進により、低学年向けの「キャリア教育型インターンシップ」や、1dayの業界理解イベント(オープン・カンパニー)が多くの企業で実施されています。
企業としても、早期に学生と接点をもち、自社への理解や志望度を高めたいという意図から、年次を問わず広く受け入れる傾向にあるのです。
学生側も、学年が低いうちから業界や職種への理解を深めておけば、就活本番でのミスマッチを避けやすくなります。
ただし、実務に深く関わるような長期型インターンシップの場合は、ある程度の基礎知識や学習経験が求められることが多く、3年生以上が対象になることもあります。
自分のスキルや目的に応じて、年次に合ったインターンシップを選ぶことが重要です。
インターンシップを実施している企業の割合
近年、インターンシップを実施する企業は急増しており、リクルートの調査によれば、従業員規模に関係なく約70〜80%の企業が何らかの形でインターンシップをおこなっていると報告されているのです。
特に大手企業やIT・メーカー系企業では、高い割合でインターンシッププログラムが導入されています。
これは学生の早期接触を狙った採用活動の一環でもあり、企業にとっては「自社を知ってもらう場」「採用選考の前段階」として位置づけられています。
一方で、採用とは無関係にCSR(企業の社会的責任)として職業体験を提供している企業もあり、その内容や目的は多様です。
中小企業やベンチャー企業でも、採用ブランディングの一環として、短期またはプロジェクト型のインターンシップを導入するケースが増加傾向です。
学生から見ても「その企業で働くイメージ」をつかむチャンスとして重要視されており、今やインターンシップは就活における必須ステップとなりつつあります。
【企業側】インターンシップの内容例を期間別に紹介
インターンシップは期間によって内容や目的が大きく異なります。
短期であれば企業理解や業界研究が中心になりますが、長期になれば実務への参加や成果創出が求められることもあります。
企業側は、期間ごとに学生に求めるゴールを明確にし、それに応じた内容設計をおこなうことが重要です。
ここでは、インターン期間ごとの具体的な内容例と設計のポイントを紹介します。
- 1dayの場合
- 3days〜1週間前後の場合
- 長期間の場合
1dayの場合
1dayインターンシップは、限られた時間の中で学生に企業の魅力や業界の理解を深めてもらうことを目的とした最も短期間のプログラムです。
新卒採用の第一接点として活用されることが多く、母集団形成や企業ブランディングの役割も担っています。
内容としては、会社説明会+グループワークという構成が定番です。
たとえば、「企業が抱える架空の課題をチームで解決するワーク」や、「先輩社員との座談会」を組み合わせることで、短時間でも印象的な体験を提供できます。
また、業界の基本構造や働き方について説明するパートも重視されます。
1dayプログラムでは、参加者に「この企業は雰囲気がよい」「社員の人柄が魅力的だった」と思ってもらえる設計が重要です。
そのため、社員との距離感が近くなるような構成や、双方向コミュニケーションを意識した企画が効果的です。
3days〜1週間前後の場合
3days~1週間のインターンシップは、1dayよりも踏み込んだ業務体験や企業理解ができる中期型プログラムです。
この期間では、より実務に近い業務を疑似体験させたり、部門別の仕事紹介、チームでの成果発表などを通じて、学生が成長を実感しやすい内容を設計できます。
たとえば、営業職であれば「顧客ニーズを分析して提案資料を作成し、ロールプレイ形式でプレゼンする」といった実践的なワークが可能です。
エンジニア職志望の学生には、「簡単なWebアプリ開発」や「コードレビュー体験」などを盛り込むことで、実務理解が深まります。
この形式では、最終日に成果発表やフィードバック会を設けることで、学生に達成感をもたせると同時に、企業側も学生の素質や取り組み姿勢を把握する材料を得られます。
選考直結型ではない場合でも、将来の応募につながる印象的な体験の提供が重要です。
長期間の場合
長期インターンシップは、一ヶ月以上にわたって学生が実際の業務に携わる形式で、特にベンチャー企業やIT系企業で広く導入されています。
即戦力となる人材の発掘・育成を目的としており、学生を「一人の戦力」として扱うのが特徴です。
内容としては、マーケティング施策の実行、SNS運用、Webサイトの改善提案、プログラミングや開発業務、データ分析業務など、社員と同様のプロジェクトに参加するケースが多く見られます。
週三日〜五日勤務で三ヶ月〜半年にわたるプログラムも一般的です。
長期インターンシップでは、学生に責任ある仕事を任せられるため、意欲や主体性が評価の対象になります。実績次第では、早期選考や内定直結のオファーにつながることもあるでしょう。
企業側にとっても、採用リスクを下げつつ長期的な関係構築ができるため、非常に効果的な採用戦略の一環とされています。
学生に人気のインターンシップ内容を紹介
インターンシップを実施するうえで重要なのは、「学生にとって魅力的であるかどうか」です。
ただ情報提供するだけではなく、学生が成長を実感できたり、「また参加したい」と思える体験を提供することが、企業イメージや採用効果の向上に直結します。
ここでは、実際に学生の評価が高かったインターンシップの内容を紹介します。
- 印象に残るインターンシップ内容
- 面白いと感じるインターンシップ内容
次回のプログラム設計やブラッシュアップの参考にしてください。
印象に残るインターンシップ内容
学生にとって印象に残るインターンシップとは、単なる会社説明にとどまらず、「実際に自分が働いているような感覚を味わえたかどうか」が大きなポイントになります。
そのため、実務に近いワークや、社員と密に関われる構成が特に高評価を受けています。
たとえば、「顧客向けの提案資料を自分たちで考え、社員にプレゼンする」「プロジェクトチームの一員として業務改善案を考える」など、アウトプットが求められるプログラムは印象に残りやすく、自信にもつながるでしょう。
また、業務に対するフィードバックを社員から受けられる機会があると、学生は自身の成長を実感しやすくなります。
加えて、「社員との交流会」や「1on1面談」を設けることで、働くイメージが具体化し、企業との距離も近くなります。
こうしたリアルな体験と対話こそが、インターンシップ後の企業理解を深め、「この会社で働きたい」というモチベーションにつながるのです。
面白いと感じるインターンシップ内容
「面白かった」と感じるインターンシップの多くは、エンタメ性やゲーム性を取り入れた内容や、普段の大学生活では味わえない“非日常感”を体験できたプログラムです。
特に、短期インターンシップでは“楽しさ”が参加満足度に直結しやすい傾向があります。
たとえば、経営シミュレーションゲームや商品開発コンペ形式のワークショップなど、自分のアイデアをカタチにできるプログラムは人気です。
また、チーム対抗でアイデアを競う形式にすると、自然と主体性や協調性も発揮され、学びと楽しさのバランスが取れた時間になります。
さらに、「実際に現場を見学し、プロジェクトの裏側を知れた」「社内ツアーで最新設備を見られた」といった“体験型”のコンテンツも高評価です。
学生にとっては、企業の“普段見えない一面”に触れることができ、記憶に残るインターンシップになります。
面白さを演出することは、参加率やSNSでの拡散にもつながる重要な要素です。
インターンシップを企画する上でのポイント3つ
効果的なインターンシップを実施するためには、単にプログラムを用意するだけでなく、以下の点が不可欠です。
- ターゲット設定を明確にする
- 社内でインターンシップの目的を共有する
- 目的に合った期間・内容のインターンシップを検討する
学生にとって有益であり、企業にとっても採用やブランディングにつながる内容にするためには、事前準備と関係者の連携が重要になります。
ここでは、インターンシップ企画において企業が必ず押さえておきたい3つのポイントを具体的に解説します。
ターゲット設定を明確にする
インターンシップの企画段階で最初におこなうべきことは、「誰に来てほしいのか」を明確にすることです。
目的なく学生を集めても、結果として採用や企業理解にはつながりません。
対象とする学年(1年生〜大学院生)、学部(文系・理系)、志望職種(営業・技術・企画など)を具体化しましょう。
たとえば、開発部門への採用を視野に入れているなら、「情報系学部の3年生で、プログラミング経験がある学生」といったように、条件を絞り込むことで、プログラム内容も参加者に合った深度に調整できます。
ターゲットが明確になると、広報の方法や告知文の言葉選び、使用する媒体(ナビサイト、SNS、大学経由など)も的確に設定しやすくなります。
結果として、企業と学生の間にミスマッチが起こりにくく、双方にとって有意義な体験となるのです。
社内でインターンシップの目的を共有する
どれほど優れたインターンプログラムを設計しても、社内の理解と協力が得られなければ、満足度の高い実施は難しくなります。
そこで重要なのが、「インターンシップの目的を社内全体で共有すること」です。
採用担当者だけでなく、現場の社員やマネジメント層にも目的を伝え、共通認識をもつことが成功の鍵です。
たとえば、「将来の採用候補として関係構築を図る」「自社の認知度を高める」「学生に業界理解を促す」など、何をゴールとするかを言語化し、社内資料や説明会などで全員に周知しましょう。
現場社員が学生に接する機会がある場合、あらかじめロールや役割分担を明確にしておくと、スムーズな運営につながります。
また、協力を得るためには、インターンシップによって得られる“社員側のメリット”(育成力の向上、若者との交流による刺激など)を伝えることも効果的です。
目的に合った期間・内容のインターンシップを検討する
インターンシップの設計において、企業が陥りがちなミスが「期間ありき」で内容を考えてしまうことです。
大切なのは、まず“何のためにインターンシップをおこなうのか”という目的を定め、それに見合った期間・内容を逆算して設定することです。
たとえば、「学生に企業理解を深めてもらいたい」が目的であれば、1dayや3daysの短期でも十分でしょう。
一方、「実務適性を見極めたい」「内定直結型の採用につなげたい」という目的ならば、数週間〜数ヶ月に及ぶ長期インターンシップのほうが適しています。
内容も同様に、目的に応じて変える必要があります。単なる業務紹介ではなく、現場との接点やアウトプット機会を組み込むことで、学生側も主体的に取り組みやすくなるでしょう。
インターンシップ設計は「企業の都合」ではなく、「目的と参加者のメリット」両方を満たす設計が重要です。
『コードリッジ(coderidge)』なら自社とマッチするインターンシップ生を募集できる
「せっかくインターンシップを実施しても、自社の文化や仕事内容にマッチする学生が集まらない」
そんな課題を抱えている企業にこそ活用していただきたいのが、『コードリッジ(coderidge)』です。
『コードリッジ』は、エンジニアとしての実践力を備えた新卒人材と、即戦力を求める企業とをマッチングする専門サービスです。
特徴的なのは、未経験からでも実務で通用するスキルを育成できる自社研修プログラムの存在があります。
現役エンジニアが開発・運営するカリキュラムにより、学生は確かな基礎とチーム開発の素地を身につけた状態で企業とのマッチングが可能です。
企業側は、学歴や経験よりも「実務に活かせるスキル」「カルチャーフィット」に重きを置いた選考が可能になり、自社のニーズに合った学生との効率的な出会いが実現します。
インターンシップ受け入れ後の採用率向上や、研修コスト削減にもつながるのが大きな強みです。
エンジニア志望の学生に向けた質の高いマッチングを実現したい企業は、ぜひ『コードリッジ(coderidge)』をご活用ください。
▼「自分のスキルが活かせる内定直結インターンを探したい…」
『コードリッジ(coderidge)』は、インターンに繋がる”無料”WEBエンジニア養成プログラミング!
まずはLINEで詳しく話を聞いてみる!登録はこちらから!
まとめ
インターンシップは、企業と学生の双方にとって非常に価値のある取り組みです。
学生にとっては、業界理解や自己成長、企業選びの判断材料となり、企業側にとっては、自社に合う人材との接点をもち、将来の採用につなげるための重要な機会になります。
その一方で、目的が曖昧だったり、学生の期待に応えられないプログラムでは、企業の印象を下げてしまうリスクもあります。
だからこそ、ターゲット設定や社内の目的共有、期間・内容の設計といった基本を押さえたうえで、学生にとって「参加してよかった」と思える体験を提供することが大切です。
また、エンジニア職など専門性が求められる分野では、『コードリッジ(coderidge)』のようなサービスを活用することで、実践力のある学生との効果的なマッチングが可能になります。
自社の魅力を伝え、将来の採用へとつながるインターンシップを成功させるために、ぜひ本記事の内容を活かして、戦略的な企画・運用をおこなってください。
▼「自分のスキルが活かせる内定直結インターンを探したい…」
『コードリッジ(coderidge)』は、インターンに繋がる”無料”WEBエンジニア養成プログラミング!
まずはLINEで詳しく話を聞いてみる!登録はこちらから!
大学からプログラミングを始めるなら、
コードリッジ!
空き時間に完全無料でエンジニアに。
まずはLINE登録!
この記事を読んだあなたにおすすめ
記事を検索
まずはLINE登録!体験講座情報も!
LINE登録へ