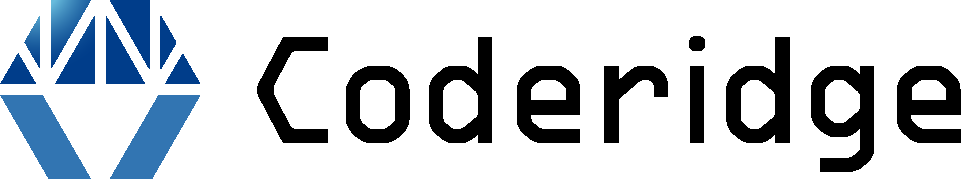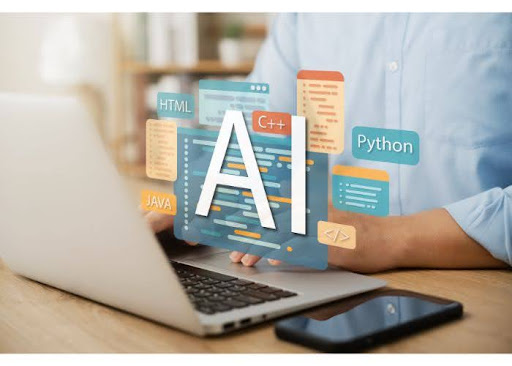
「生成AIってよく聞くけど、実際に何ができるの?」「初心者でも使いこなせるの?」と疑問に思っていませんか?
近年、ChatGPTをはじめとした生成AIの進化は目覚ましく、文章・画像・音声などさまざまなコンテンツを自動で作り出す技術が急速に広がっています。
学生や社会人まで、学習や仕事の現場でAIを活用する機会が増えています。生成AIを正しく使いこなすには、その仕組みを理解することが不可欠です。
本記事では、生成AIの基本から具体的な使い方、初心者におすすめの活用方法までをわかりやすく紹介するので、ぜひチェックしてください。
▼「自分のスキルが活かせる内定直結インターンを探したい…」
『コードリッジ(coderidge)』は、インターンに繋がる”無料”WEBエンジニア養成プログラミング!
まずはLINEで詳しく話を聞いてみる!登録はこちらから!
生成AIとは
生成AIとは、人間の指示(プロンプト)をもとに、文章・画像・音声・動画などのコンテンツを自動で生成する人工知能のことです。
従来のAIが「分析・分類」に使用されていたのに対し、生成AIはまるで人間のように創作や提案を行えるのが大きな特徴です。
代表的な例として、ChatGPTやStable Diffusion、DALL·E、GitHub Copilotなどが挙げられます。
これらのAIは、膨大なデータを学習し、パターンを予測する「ディープラーニング(深層学習)」の技術をベースにしています。
ビジネスや教育、クリエイティブの分野でも、生成AIはアイデア出しの補助や自動化ツールとして導入されており、今後さらに進化していくことが期待されている分野です。
生成AIの種類
生成AIと一口に言っても、その用途や生成するコンテンツの種類によって、その技術はさまざまです。
文章を作るものに限らず、画像・音声・動画・プログラムコードなど、特定の分野に特化したAIが次々に登場しています。
本章では、代表的な6つの生成AIを取り上げ、それぞれがどのような分野で活用されているのかを詳しく解説します。
自分の目的に合ったAIを選ぶためにも、まずは種類ごとの違いを理解しておきましょう。
文章生成AI
文章生成AIは、人間が与えたプロンプトに応じて自然な文章を出力するAIで、生成AIの中でも最も広く利用されている分野です。
代表的な文章生成AIには、ChatGPTやGoogle Geminiがあり、ニュース記事やブログ投稿、SNSのキャプション、メール文など、さまざまな文書作成をサポートします。
このAIは、膨大なテキストデータを学習しているため、話し言葉と書き言葉の違いにも対応し、自然な文章構造を再現できます。教育やマーケティング分野でも注目されており、学生であればレポートの構成案や自己PRのたたき台づくりなどにも活用可能です。
文章生成AIは、使い方次第で調査アシスタントや編集者のような役割を果たせる柔軟性を持っており、初心者でも比較的すぐに効果を実感しやすい分野です。
画像生成AI
画像生成AIは、テキストの指示からイラストやリアルな画像などを自動的に作り出すAIです。
代表的なツールには、Stable Diffusion、DALL·E、Midjourneyなどがあり、芸術表現から広告素材作成まで幅広く使われています。
使い方はシンプルで、「猫が本を読んでいるイラスト」や「夕暮れの都市の風景」といったテキストを入力するだけで、数十秒ほどで高品質な画像が生成されます。
専門的なスキルがなくても、自分のアイデアを視覚的に表現できるようになるでしょう。
学術発表や資料づくりの挿絵、ブログやSNS用のアイキャッチ画像の作成などにも便利で、今後さらなる発展と活用が期待されている分野です。
音声生成AI
音声生成AIは、テキストをもとに音声を合成する技術で、ナレーションやアナウンス、自動音声応答(IVR)などに利用されています。
近年では、音声の自然さや抑揚、感情表現の精度が大きく向上し、まるで人間が話しているかのような品質の音声が得られるようになりました。
代表的な音声生成AIには、VOICEVOX、Google Cloud Text-to-Speech、Amazon Pollyなどがあり、YouTube動画のナレーション、教育コンテンツ、読み上げツールとして活用されています。
また、既存のキャラクターの声の再現できるほか、音声の読み上げ速度、声のトーン、感情の強さを細かく調整可能です。
語学学習やプレゼン練習、音声付き教材の作成など学びの場でも役立つ場面が多く、活用の仕方次第で大きな時間短縮や作業効率化が期待できる分野です。
動画生成AI
動画生成AIは、画像やテキスト、音声データをもとに映像を自動生成する技術です。これまでは専門的なスキルが必要だった動画制作が、簡単な指示を入力するだけで手軽におこなえるようになってきました。
代表的な動画生成AIにはPictory、Runway、Synthesiaなどがあり、プレゼン動画や商品紹介ムービー、教育用コンテンツの制作に広く活用されています。
たとえば、「製品の特徴を紹介する60秒の動画を作成」「英語ナレーション付きでアニメーション表示」などの指示を出すと、テンプレートを活用したプロ品質の動画が数分で生成されます。
人物の動きや字幕、音声の挿入も自動化されており、作業時間の大幅な短縮が可能です。特に、動画編集に時間をかけにくい学生や広報担当者にとって、動画生成AIは効率的な時短ツールとして注目されています。
コード生成AI
コード生成AIは、プログラミングの知識が浅い人でも、自然な文章で指示を出すだけでコードを自動生成できるAIです。
代表的なコード生成AIにはGitHub CopilotやAmazon CodeWhispererがあり、開発者の作業を大幅に効率化しています。
たとえば、「JavaScriptでカウントアップするボタンを作成」と入力するだけで、正しい構文のコードを提示してくれるため、初心者や学習中のユーザーにとって非常に頼れる存在です。
さらに、コードの改善提案やリファクタリング、バグ修正にも対応しており、学びながら実践力を高められます。これにより、学習中の学生や就職を目指す未経験者でも、実際に手を動かしながら効率よくスキルを習得できるようになりました。
生成AIの中でも、エンジニアを目指す人にとって特に活用価値の高い分野です。
マルチモーダルAI
マルチモーダルAIとは、文章・音声・画像・動画など、異なる種類の情報をまとめて理解し、活用できる高度な生成AIです。
従来の生成AIは、テキストだけ、音声だけといった単一の情報に対応するものが主流でしたが、マルチモーダルAIはそれらを同時に扱い、組み合わせて処理することが可能です。。
たとえば、写真の内容を読み取って説明文を自動で作成したり、文章と図を組み合わせたスライド資料を作ったりといったことが可能です。
最近では、GPT-4やGoogle Geminiといった最新の生成AIが、このマルチモーダル技術に対応しています。
たとえば「この画像をもとに商品紹介を書いて」「図を入れた説明資料を作って」といった複雑な依頼に対して、AIが一貫して処理できるようになっています。
教育、資料作成、広告、デザインなど、さまざまな分野での活用が進んでおり、マルチモーダルAIは今後、生成AIの中心的な存在になるといえるでしょう。
【初心者向け】生成AI使い方のコツ
生成AIは誰でも使える便利なツールですが、ただ話しかけるだけで理想通りの結果が得られるとは限りません。
特に初心者が活用する際は、「どのように伝えるか」が非常に重要なポイントになります。
この章では、生成AIをスムーズに活用するための基本的なコツを5つ紹介します。どれもすぐに実践できる内容なので、これからAIを使ってみたい方、うまく使いこなせないと感じている方はぜひ参考にしてください。
目的をはっきり伝える
生成AIに指示を出す際、「何をしてほしいのか」目的を明確に伝えることが最も重要です。
人間同士のコミュニケーションでも、曖昧な依頼では意図が伝わらないように、AIもまた不明確な指示に対しては、意図から外れた不完全なアウトプットを返す可能性があります。
たとえば、「ブログを書いて」と漠然と指示するのではなく、「就活生向けに自己PRの書き方を紹介するブログ記事を書いて」と具体的に伝えると、AIは適切な内容を生成できます。
さらに、「〇〇についての説明を100文字で」「ポジティブなトーンでまとめて」など、成果物の形式やトーンといった条件を補足すると、精度は一層向上します。
目的を明確にすることはAIとの対話の精度を高めるだけでなく、自分自身のアウトプットの質や意識を高めるうえでも効果的です。プロンプト設計の第一歩として、意識して取り組んでいきましょう。
役割を指定する
生成AIは「どのような立場で答えるか」をあらかじめ指示すると、出力される内容やトーンが大きく変わります。
この手法は「ロール指定」と呼ばれ、プロンプトを調整するうえで非常に効果的です。たとえば、「あなたは就職支援の専門家として答えてください」と指示すれば、AIはその役割にふさわしい語彙やアドバイスを用いて回答します。
同じ質問でも、学生の目線、先生目線、エンジニア目線など、役割によって文章の深さや方向性が変わるため、読み手に合わせた表現が可能になります。
また、話し方を変える際にもロール指定は有効です。「親しい友人として」「ビジネスの上司として」などと指定することで、文体や丁寧さも自動的に調整されます。
AIの使い方に慣れていない人にとって、このテクニックを活用することは、生成AIとの対話を格段にスムーズにする手助けとなるでしょう。
出力形式をあらかじめ決める
生成AIに何かを依頼する際は、出力してほしい形式を最初に指定することで、意図通りの結果が得られやすくなります。
たとえば「箇条書きでまとめてください」「表形式で教えてください」「500文字以内で」など、形式に関する条件を具体的に伝えることで、内容だけでなく見やすさも整ったアウトプットが可能です。
こうした形式指定をしないまま依頼すると、長文になりすぎたり、話が逸れてしまったりする場合があります。特にレポートや資料作成、文章の構成を必要とする場面では、フォーマット指定が非常に重要です。
また、繰り返し同じ形式で出力させたい場合にも、テンプレートとして保存しておけば効率的に作業が進みます。このように形式を意識することで、AIの出力精度が高まり、より実用的な活用がしやすくなります。
参考例を提示する
生成AIに依頼する際は、参考例を提示することが重要です。なぜなら、自分のイメージを言葉だけで完全に伝えるのは難しく、参考例があることでAIが意図をより正確に理解しやすくなるからです。
たとえば、「以下の文章を参考にしてください」「この書き出しのようなスタイルで」「例文のフォーマットを真似てください」と具体的に示すことで、狙い通りの出力を得やすくなります。
これは文章だけでなく、見出しの構成やトーン、語調の指定にも効果的です。人間にとっての見本は、AIにとっての正解のヒントとなるでしょう。
目的に合ったアウトプットを引き出したいときほど、参考例をうまく使うことで期待するクオリティに近づけやすくなります。
繰り返し調整する
生成AIを効果的に使うためには、繰り返し調整することが大切です。生成AIは賢いツールですが、一度のやり取りで完璧な結果が得られるわけではありません。
たとえば、最初の出力が自分の意図と少しずれていた場合でも、「ここをもっと簡単に」「この部分を短くして」「語尾を統一して」などと具体的にフィードバックを重ねることで、理想の文章に近づけていけます。
このように試行錯誤しながら少しずつ調整していく姿勢が、生成AIを上手に活用する上で欠かせない工程です。修正指示を具体的に出すほど、生成AIの出力も洗練されていきます。
逆に、一度の回答だけで諦めてしまうと、本来得られるはずの成果を逃すことにもつながります。生成AIは「対話型ツール」です。人と会話するように少しずつ調整していく姿勢が、最適なアウトプットを得るためのコツとなります。
初心者こそ、この「繰り返し調整」を恐れず、積極的に活用していきましょう。
▼「自分のスキルが活かせる内定直結インターンを探したい…」
『コードリッジ(coderidge)』は、インターンに繋がる”無料”WEBエンジニア養成プログラミング!
まずはLINEで詳しく話を聞いてみる!登録はこちらから!
生成AIの活用事例
生成AIはアイデア出しや文章作成だけでなく、日常業務や学習にも幅広く活用されています。
初心者でも始めやすい使い方から、業務の効率化につながる実践的な活用法まで、目的に応じた柔軟な使い方が可能です。
この章では、学生にも社会人にも役立つ、代表的な5つの活用事例を紹介します。どれも今日からすぐに試せる内容なので、ぜひ実際に取り入れてみてください。
Webサイトやブログ記事の原稿作成
Webサイトやブログ記事の作成には、生成AIの活用が非常に効果的です。Webサイトやブログ記事の作成には、アイデアの構成から見出し、本文執筆、リード文、メタディスクリプションの記述など、多くの工程があります。
こうした作業も、生成AIを活用すればスムーズに補助できるため、文章作成に苦手意識がある人でも安心して取り組むことが可能です。
たとえば、「SEOを意識したブログ記事の構成を考えて」「このキーワードで導入文を書いて」といった具体的指示を出すことで、AIは論理的かつ読みやすい文章を提案してくれます。
さらに、言い回しの修正や文章の要約、校正にも使えるため、クオリティを保ちながら執筆時間を短縮できます。
学生のレポート、フリーランスのライターの執筆活動、企業の広報担当者のコンテンツ制作など、文章が必要なあらゆる場面で、生成AIは頼れる共同執筆者となるでしょう。
履歴書・職務経歴書の文面作成
就職活動や転職の際に必須となる履歴書・職務経歴書の作成にも、生成AIは大いに活用できます。
特に「志望動機がうまく書けない」「自己PRで何をアピールすればよいか悩む」という学生や若手社会人にとって、AIの提案は大きな助けとなるでしょう。
たとえば、「大学時代にゼミで研究した内容を元に自己PRを作成してください」「営業経験をもとに成果を強調した志望動機を100文字で」のように具体的に指示を出すことで、自身の経験に合った説得力のある文面を作成できします。
また、敬語表現や文法のチェック、全体のトーンの調整にも使えるため、より自然で整った文章に仕上げることが可能です。最終的な確認や調整は自分でおこなう必要がありますが、AIにたたき台を作ってもらえるだけでも、作業の負担やストレスは大きく軽減されるでしょう。
英語・プログラミングなどの学習補助
生成AIは、英語やプログラミングなどのスキル学習において、強力なサポートツールとして活用できます。たとえば英語学習では、単語の意味だけでなく文脈に応じた使い方を例文付きで教えてくれるほか、英作文の添削もおこなえます。
ChatGPTのような対話型AIなら、会話練習の相手にもなってくれるため、発話力の向上にも効果的です。
一方、プログラミング学習では「このコードの意味を説明して」「エラーの原因を教えて」といった質問に即座に答えてくれるため、自学自習がはかどります。特に初心者にとっては、細かい疑問を気軽に解消できる点が大きなメリットといえるでしょう。
さらに、理解があいまいな部分を補足してもらったり、練習問題を作ってもらったりすることも可能です。生成AIはまさに「マンツーマンの家庭教師」のように、個別に寄り添ってくれる存在といえるでしょう。
試験対策の要約や問題作成
生成AIを活用すれば、試験対策の効率を大幅に高めることが可能です。
教科書や講義資料の内容を入力すれば、その要点を簡潔にまとめ、重要なキーワードを抽出してくれるため、情報の整理が格段にしやすくなります。
また、「この内容から穴埋め問題を作って」「記述式の過去問風の問題を出して」などと依頼すれば、自分専用の問題集を作ることも可能です。さらに、解答とその解説も一緒に出力できるため、問題演習から振り返りまでを一貫しておこなえるのが特徴です。
自分の苦手分野を集中的に対策したり、記憶の定着に効果的なアウトライン要約を使って復習したりと、AIをうまく活用することで学習効率は飛躍的に向上します。試験前の追い込みにも心強い味方となるでしょう。
プレゼン資料の構成づくり
効率よく質の高いプレゼン資料を作成したいなら、生成AIの活用が効果的です。
プレゼンテーションの準備には、話す内容の整理やスライドの構成を練る作業が不可欠ですが、慣れていないと時間も労力もかかります。生成AIは、この「構成づくり」を大きくサポートしてくれます。
たとえば、「新規サービスの提案資料の構成を作って」「研究発表のスライド構成を5枚にまとめて」などと指示すれば、論理的な流れで段取りを提案してくれます。
さらに、各スライドの要点やタイトル、補足説明文まで自動生成可能なため、たたき台としてすぐに使えるクオリティの高い提案が得られます。自分で考える時間が短縮されるだけでなく、抜け漏れのないプレゼン設計にも役立つのが魅力です。
学生のゼミ発表、就活の自己PR資料、社内報告など、あらゆるプレゼンシーンで生成AIは優秀な「構成アドバイザー」として活躍してくれるでしょう。
『コードリッジ(coderidge)』なら初心者でも生成AIの使い方をマスターできる
生成AIを活用してみたいけれど、「どうやって学べばいいのか分からない」「正しい使い方ができているか不安」という方も多いのではないでしょうか。
そんな初心者の方におすすめなのが、『コードリッジ(coderidge)』です。『コードリッジ(coderidge)』は、エンジニアとして即戦力を目指す新卒人材と、AI・ITスキルを求める企業をつなぐマッチングプラットフォームです。
『コードリッジ(coderidge)』では、生成AIを含む実践的なスキルを、精鋭の現役エンジニアが丁寧に指導します。未経験者向けに設計されたカリキュラムで、段階的にスキルを習得できるのが特徴です。
さらに、学習後はスキルレベルに合った企業とのマッチング支援や、キャリア相談まで一貫してサポートいたします。生成AIを使いこなす力を確実に身につけ、将来の武器に変えていきたい方にとって、『コードリッジ(coderidge)』は、理想的な環境が整っています。
迷っているなら、まずは一歩踏み出してみましょう。
▼「自分のスキルが活かせる内定直結インターンを探したい…」
『コードリッジ(coderidge)』は、インターンに繋がる”無料”WEBエンジニア養成プログラミング!
まずはLINEで詳しく話を聞いてみる!登録はこちらから!
まとめ
生成AIは、文章や画像、音声などを自動で作成できる便利なツールです。使い方を理解すれば、学習や仕事の効率を大幅に高めることが可能です。
初心者でもコツを押さえればすぐに活用でき、アイデアの整理や資料作成といった実務にすぐに活用できる点が大きな魅力です。正しい知識を身につけ、実践を重ねることで、AIとの連携は強力な武器になります。
まずは身近なところから試して、生成AIを「新しいスキル」として使いこなしていきましょう。
▼「自分のスキルが活かせる内定直結インターンを探したい…」
『コードリッジ(coderidge)』は、インターンに繋がる”無料”WEBエンジニア養成プログラミング!
まずはLINEで詳しく話を聞いてみる!登録はこちらから!
大学からプログラミングを始めるなら、
コードリッジ!
空き時間に完全無料でエンジニアに。
まずはLINE登録!
この記事を読んだあなたにおすすめ
記事を検索
まずはLINE登録!体験講座情報も!
LINE登録へ