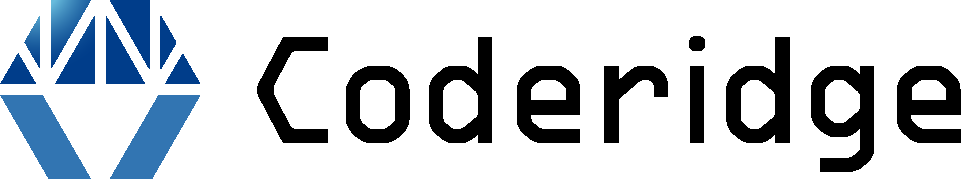「生成AIを使ってもうまく意図通りの出力が得られない」「プロンプトの書き方がわからない」そんな悩みを抱える方は多いのではないでしょうか。
生成AIの精度や便利さは年々進化しています。しかし、それを最大限に活かすためには“プロンプトエンジニアリング”という考え方が欠かせません。
つまり、AIに「何をどう伝えるか」が成果の質を大きく左右するといえ、伝え方のコツを知っていることが重要になります。
本記事では、生成AIを活用する上で知っておくべきプロンプトの基本から書き方のコツ、具体的な活用シーン、そして注意点までを徹底解説します。
初心者から業務活用を目指す方まで、どなたでも参考にできる内容です。ぜひ、最後までご覧ください。
▼「自分のスキルが活かせる内定直結インターンを探したい…」
『コードリッジ(coderidge)』は、インターンに繋がる”無料”WEBエンジニア養成プログラミング!
まずはLINEで詳しく話を聞いてみる!登録はこちらから!
生成AIのプロンプトとは
生成AIとは、文章・画像・コードなどのアウトプットを自動生成するAI技術のことです。そのなかで「プロンプト」とは、ユーザーがAIに対して出す“指示文”や“問いかけ”を指します。
たとえば、「SNS投稿文を考えて」「会議の要約をして」といったテキストがプロンプトにあたります。
このプロンプトの内容次第で、AIの応答内容は大きく変わるでしょう。単に質問するだけでは不十分であり、目的や背景、出力形式などをしっかり伝えることで、より精度の高い結果が得られます。
つまり、プロンプトは生成AIを活用する上で最も重要な“操作インターフェース”といえるでしょう。
現在では「プロンプトエンジニアリング」と呼ばれるスキルとして注目され、ビジネスシーンでも活用が進んでいます。AIを効率よく使いたいなら、まずはプロンプトの考え方から理解を深めておくことが必要です。
生成AIのプロンプトの書き方とコツ
生成AIの力を最大限に引き出すには、適切なプロンプトの作成が欠かせません。単に「これを作って」と生成AIに頼むだけでは思った通りの結果が得られず、精度も安定しない可能性があります。
ここでは、誰でも実践できるプロンプト作成の基本と、出力の質を高めるための以下に記載している7つのコツを紹介します。
ビジネス・学習・日常活用まで、どの場面にも応用できるテクニックを具体的に記載しておりますので、ぜひ参考にしてください。
- 目的を明確に伝える
- 具体的な条件や制約を示す
- ターゲット(ペルソナ)を伝える
- 出力例を添える
- 期待するスタイルやトーンを指定する
- 段階的に指示を出す
- NG例や避けてほしい表現を伝える
目的を明確に伝える
生成AIは非常に多機能な反面、指示が曖昧だと出力がブレやすくなります。そのため、まず最も重要なことは「何のために使うのか」を明確に生成AIに伝えることです。
たとえば、「就活用の自己PR文を作って」とだけ伝えるよりも、「新卒採用向けに、面接で話す自己PR文を300文字以内で作成してほしい」というように、目的と用途を具体的に伝えるほうが生成の精度は大きく向上します。
AIは人間のように文脈を推測する力にはまだ限界があるため、出力の「意図」と「用途」をしっかり定義しておくことが重要です。
資料作成なのかSNS投稿なのか、アイデア出しなのか、まずは何のために生成してもらうのかを一言で伝えるだけでも回答の方向性が大きく変わります。
生成の結果に納得がいかないときは、まず自分の目的設定が曖昧になっていないかを見直すと、改善につながるケースが非常に多いです。
具体的な条件や制約を示す
生成AIに期待する出力には、「どんな条件で」「どのように表現してほしいか」といった具体的なルールを伝えることで、より精密で実用的な結果が得られます。
たとえば、「5つのアイデアを箇条書きで提示して」「文字数は200字以内にして」「です・ます調で書いてほしい」などの条件を加えるだけで、生成される文章の質は格段に向上するでしょう。
これは人間に指示する際のマニュアル作成にも似ており、AIにとっても「どこまでを守ればよいのか」が明確になります。その結果、想定通りの応答が返ってきやすく、精度の高い生成結果となるでしょう。
また、数値化できる制約(例:◯文字以内、3つ挙げて、○○形式で)を含めると、フォーマットも整いやすく、再編集の手間が減るという実用的なメリットもあります。
曖昧なまま任せるのではなく、必要な条件は最初に伝えておくことが、プロンプト設計の基本といえるでしょう。
ターゲット(ペルソナ)を伝える
生成AIに文章や提案を作ってもらう際、誰に向けたものかを明示することで、より的確な出力が可能です。この「誰に伝えたいか」という視点を、マーケティングの世界では「ペルソナ」と呼びます。
たとえば「大学生向け」「40代の働く女性向け」「新入社員向け」といったターゲットの情報を加えることで、文体・言葉選び・内容の深さが自動的に調整されやすくなります。
AIは与えられた情報をもとに内容を組み立てるため、ペルソナが明確であればあるほど、より“刺さる”コンテンツになるでしょう。
一方で、ターゲットが曖昧な場合は、「誰に向けた文章なのかわからない」と感じるようなぼんやりとしたアウトプットになりがちです。
「○○向けに優しく解説してください」「○○の知識がない人にも伝わるように説明して」といった一文を加えるだけでも、出力品質は大きく向上します。
出力例を添える
AIに期待する形式や方向性を明示するために、あらかじめ“理想の出力例”を提示するのは非常に効果的なテクニックです。
たとえば、「このようなトーンで」「以下のような構成で」として、自作の一文やフォーマット例を添えておくと、AIはそのスタイルや論理構造を模倣しやすくなります。
人間同士でも「こういう感じでお願い」と具体例を出されると理解しやすいように、生成AIも参考となるサンプルがあれば、学習済みのパターンをもとに似た形で出力してくれます。
特に、文体のトーンや段落構成、論理展開の順番といった“スタイル要素”を整える際に有効です。
「文章の例はこうです」「以下のように構成してください」といったテンプレート的な使い方ができるため、毎回の指示の質も安定し、再現性の高い活用が可能になります。
期待するスタイルやトーンを指定する
生成される文章の印象を大きく左右するのが、「スタイル」や「トーン」の設定です。たとえば、「フランクな口調」「論文調」「プレゼン資料向け」によって、AIが選ぶ言葉や表現は変わってきます。
そのため、「敬語で丁寧に」「専門用語は使わず、初心者向けに」「親しみやすいカジュアルな語り口で」といった指定を加えることが重要ですAIは指示されたトーンを忠実に再現する特性があるため、意図した印象を伝えやすくなります。
特にビジネスや教育現場での活用では、対象読者に応じたトーンの微調整が必要不可欠です。これを怠ると、意図しない堅すぎる表現や、逆に砕けすぎた表現が出力されることがあります。
文章の読み手が誰かを意識しつつ、どんなトーンで伝えたいかを明記することで、出力品質の一貫性と納得感が大きく高まります。
段階的に指示を出す

複雑なアウトプットをAIに求める場合、一度に全てを指示するのではなく、段階的にステップを踏んで指示を出すと精度が大きく改善します。
これは「ステップ・バイ・ステップ方式」とも呼ばれ、特に長文構成や構造化された文書の作成時に有効です。
たとえば、最初に「3つの構成要素を出してください」と指示し、その後で「それぞれの要素について詳しく説明してください」と段階的に進めていく方法があります。
これにより、AIが焦点をしっかり絞った上で出力でき、内容がブレにくくなるというメリットがあります。
また、プロンプト自体が長くなりすぎるのを防ぐ効果もあるため、生成の際に段階的に指示を出すことは非常に効果的となるでしょう。
一度に大量の条件を詰め込むと処理効率が落ちるため、分割しながらやり取りを進めることで、作業効率と出力精度のバランスを保つことができます。
NG例や避けてほしい表現を伝える
プロンプトを作成する際、「こういう表現は避けてほしい」といったネガティブな条件を加えることで、誤解や意図しない出力を防ぐことが可能です。
たとえば、「専門用語を使わないで」「あいまいな表現は避けてください」「ネガティブな語調にはしないでください」といった具体的な禁止事項を明記することで、生成される文章の質が安定します。
生成AIは善意で“補完”してしまう性質があるため、指定がないと過剰な飾り文や、適さない例え話を入れてしまうことがあります。そうしたミスを防ぐには、明確に「避けてほしい範囲」を伝える方法が効果的です。
また、業界によってはコンプライアンスの観点から使えない表現もあります。あらかじめNGワードやNGスタイルを定義しておくことで、ビジネス現場での運用リスクも減らせます。
積極的に“してほしくないこと”を伝える意識が、生成の精度向上に直結するでしょう。
【シーン別】生成AIのプロンプト例
生成AIは、指示の仕方ひとつでさまざまな業務を効率化できる便利なツールです。中でも「何に使いたいか」という目的別にプロンプトを工夫することで、より実践的なアウトプットが得られるようになります。
以下の5つは、マーケティング・メール作成・議事録要約・マニュアル制作・資料作成といった具体的なビジネスシーンに応じたプロンプト例です。
どれもすぐに応用できる内容であり、実務への活用を考えている方は必見です。ぜひ、ご覧ください。
- シーン①マーケティング施策のアイデア出し
- シーン②メール・チャット文の自動作成
- シーン③議事録・会議要約の自動化
- シーン④社内マニュアル・手順書の作成支援
- シーン⑤資料や企画書のたたき台作成
シーン①マーケティング施策のアイデア出し
マーケティング施策では、日々多くのアイデアが求められます。しかし、常に新しい発想を出し続けるのは容易ではありません。
そんなとき、生成AIに対して「目的」「商品概要」「ターゲット層」などを伝えた上でプロンプトを活用すれば、斬新な切り口を得るヒントとなるでしょう。
たとえば、「20代女性向けのスキンケア商品のSNSキャンペーン案を5つ、ユニークな切り口で提案してください」といった形で指示すると、実用的で比較可能な複数案が出力されます。
さらに、「実現可能性の高い順に並べて」「過去の成功事例に基づいて」など、条件を加えることで、より業務に即したアイデアが得られます。
AIは視点を変えるのが得意なため、自分では思いつかない角度からの提案が得られる点も魅力です。アイデアの起点を作る“ブレスト補助ツール”として、非常に頼れる存在となるでしょう。
シーン②メール・チャット文の自動作成
ビジネスメールやチャット文の作成は、社会人の日常業務の中で頻度が高く、なおかつ時間がかかる作業のひとつです。
生成AIを活用することで、内容に合わせた丁寧な文面を短時間で作成できるため、業務効率が大きく向上します。
たとえば、「取引先に納期延長を依頼するメール文を丁寧で誠意あるトーンで作成してください」や、「社内向けに明日の会議延期をお知らせするチャット文を短めに」といった形で指示を出すとトーンや目的に合った文章が即座に生成されます。
さらに、敬語の使い分けや締めの挨拶の工夫など、ニュアンスの調整もプロンプトで細かく伝えることが可能です。
メール作成に慣れていない新入社員や、文章作成が苦手な人にとっても、AIの活用は大きな助けになります。
シーン③議事録・会議要約の自動化
会議後の議事録作成や内容要約は、重要ながらも時間がかかる業務のひとつです。生成AIを活用すれば、録音データのテキスト化や議事メモをもとに、論点が整理されたわかりやすい議事録が短時間で完成します。
たとえば、「以下の議事録メモをもとに、要点を3つにまとめてください」「各発言の要旨を時系列で整理してください」といったプロンプトを活用することで、読み手にとって必要な情報だけを抽出した簡潔なドキュメントの生成が可能です。
特にAIは構造化された文章の整理が得意であり、話が飛びがちな会議の内容を論理的に整える役割を果たしてくれます。
議事録の品質が安定すれば、参加できなかったメンバーへの共有や、記録としての活用もスムーズになります。
シーン④社内マニュアル・手順書の作成支援
社内マニュアルや業務手順書の作成は、多くの人に伝わるように構成を整え、わかりやすい文章でまとめる必要があるため作業時間も労力もかかる業務です。
生成AIは、こうした文書作成において非常に有効なサポート役となります。たとえば、「新人向けに経費申請手順をわかりやすく説明したマニュアル文を作ってください」といったプロンプトを使えば、初心者目線に立った丁寧な内容が自動で出力されます。
さらに、「5つのステップに分けて」「箇条書きで簡潔に」「図解用の補足も含めて」といった条件を加えると、実用性がさらに高まるためオススメです。
生成AIによるたたき台があれば、内容の確認や加筆に集中でき、ゼロから作るよりも大幅に時間を削減できます。文書整備が求められるあらゆる業務で活用が進む分野です。
シーン⑤資料や企画書のたたき台作成
プレゼン資料や企画書は、構成を考えること自体に時間がかかり、いきなり書き始めるのが難しい作業のひとつです。
そんなときに役立つのが、生成AIを使って“たたき台”となる構成案や文章の下書きを生成してもらう方法です。
たとえば、「新入社員研修の企画書の構成案を、5つの項目に分けて提案してください」や、「営業提案資料の導入文と課題提示部分を考えてください」といったプロンプトを出すことでアウトラインや書き出しの方向性が得られます。
AIから得られるたたき台をもとに、自分の考えを肉付けしていくことで、作業効率が上がり、完成までの時間も大幅に短縮されるでしょう。
資料作成が多い職種の方や、企画に悩む学生・社会人にとって、生成AIにおける補助は心強い味方になります。
生成AIのプロンプトの例をいくつかご紹介しましたが、実際に実務経験を積むことでより深く生成AIに関して理解を深めることができます。『コードリッジ(coderidge)』なら、プロンプトエンジニアリングのスキルを実務レベルまで高められるため非常にオおすすめです。
生成AIでプロンプトを作成するときの注意点
プロンプトは、生成AIを使いこなす上で最も重要な操作要素です。しかし、いくつかの注意点を守らなければ意図しない出力になる可能性もあり、効率も落ちてしまいます。
以下の5つは、プロンプト作成時によくある失敗例や、避けるべき書き方・考え方の視点です。質の高いAI出力を得たい方や、業務での活用を目指す方は、ぜひ参考にしてミスを減らしていきましょう。
- 複数の指示・質問を一度に詰め込まない
- 長過ぎるプロンプトは避ける
- ネガティブ指示よりポジティブ指示を心がける
- 曖昧な言葉を避ける
- 最新モデルのAIを使用する
複数の指示・質問を一度に詰め込まない
プロンプトに情報を詰め込みすぎると、AIがどの指示を優先すべきか判断できなくなり、結果として中途半端な回答になるリスクがあります。
特に「○○について説明しつつ、△△についても意見を述べて、さらに□□の例も挙げて」といった複合指示は、意図通りの出力を得るのが難しくなります。
このようなときは、指示を1つずつ小分けにし、段階的にAIに問いかける方法がおすすめです。たとえば「まず○○について説明してください」「次に、□□についての例を挙げてください」と順を追って聞くことで、より正確で整理された出力が得られます。
AIは人間のように優先順位を判断する力がまだ未熟です。生成AIを使用する際、段階的に情報を与えていくことで、目的に沿った精度の高いアウトプットが期待できます。
長過ぎるプロンプトは避ける
プロンプトが長くなりすぎると、AIの処理負荷が高くなるだけでなく、要点がぼやけてしまう可能性があります。
情報が多いと、生成AIがどの部分を重要視すべきか迷い、結果として浅い内容やピントのずれた出力になることがあります。
文章の中で複数の条件や背景を長文で並べてしまうと、読み手(=AI)にとっての“理解コスト”が上がり、正確な応答が得られにくくなるでしょう。
そこで有効なのが、情報を整理して短く要点を伝えるテクニックです。たとえば、「3つのポイントを箇条書きで」「背景は以下の通り」など構造化された指示を使うことで、生成AIが理解しやすいプロンプトになります。
伝えたい内容を詰め込むよりも、「どの情報が必要か」を取捨選択して伝えるほうが、生成AIとのやりとりは円滑になります。
ネガティブ指示よりポジティブ指示を心がける
生成AIに対して「○○しないでください」といった否定形の指示を出すと、期待通りに動作しないことがあります。
これはAIが“しないこと”の裏にある「何をすればよいか」を判断しづらいからです。そのため、指示はできるだけポジティブな表現で伝えることが重要です。
たとえば、「難しい言葉を使わないで」ではなく「中学生でも理解できる言葉で説明してください」といった言い換えをおこなうことで、生成AIはより正確に目的を理解しやすくなります。
また、「感情的な表現は避けてください」よりも「論理的で落ち着いたトーンで書いてください」といった指示のほうが、具体的なトーンを指定でき、出力のブレも少なくなります。
ネガティブな制約ではなく、ポジティブな行動や表現で求める内容を明確に伝えることが、生成AIとの意思疎通をスムーズにし、より質の高いアウトプットにつながるでしょう。
曖昧な言葉を避ける
「いい感じに」「それっぽく」「普通に」など、意味があいまいな言葉をプロンプトに使ってしまうと、AIは適切に判断できず出力にズレが生じる原因となります。
人間同士であればニュアンスで伝わることもありますが、AIには明確な条件や定義がないと正確な解釈ができません。
たとえば、「この内容をうまくまとめて」ではなく、「以下の3つの観点で200字以内に要約してください」というように、曖昧な指示を具体的な行動や数値に落とし込むことで期待する出力に近づけることが可能です。
また、「一般的に」「多くの場合」などの表現も、できるだけ具体例や根拠とセットで伝えるようにしましょう。
AIは曖昧な指示には曖昧な答えで返してしまうため、プロンプトの明確化が成果の安定につながります。
最新モデルのAIを使用する
プロンプトの質を高めるだけでなく、AI自体の性能にも注目することが、生成の品質を大きく左右します。
生成AIは年々アップデートが重ねられ、新しいモデルほど文脈理解力や応答の一貫性・情報の正確性が向上しています。
したがって、プロンプトが同じでも、使用するAIのバージョンによって結果が大きく異なることがあるでしょう。
たとえば、古いモデルでは「箇条書きで出して」といった指示を正確に理解できなかったり、冗長な回答になることがあります。しかし、最新のモデルでは自然で的確なアウトプットが返ってくる傾向にあります。
無料プランでは旧モデルしか使えないケースもあるため、業務活用を考えている場合は、有料プランへの切り替えやAPIの活用も検討すると良いでしょう。良いプロンプトを活かすには、常に最適なAI環境を選ぶことが大前提となります。
『コードリッジ(coderidge)』なら生成AIのプロンプトエンジニアリングを習得できる
生成AIで不可欠な「プロンプトエンジニアリング」のスキルは、今後ますます注目される分野です。
しかし、独学では限界を感じることも多く、実践の場やフィードバック環境が整っているかどうかが習得の鍵になります。
そこでおすすめなのが、エンジニア育成特化型のキャリア支援サービス『コードリッジ(coderidge)』です。
『コードリッジ(coderidge)』では、現役の精鋭エンジニアが設計したカリキュラムをもとに、未経験からでもプロンプトエンジニアリングを体系的に学べます。
実際の業務で活かせるプロンプトの設計方法や、生成AIとの対話の最適化スキルを、実践的な課題を通じて身につけられるのが特徴です。
さらに、習得したスキルを活かせるインターンや企業とのマッチング機会も提供しており、学びを即キャリアに繋げることが可能です。今こそ『コードリッジ(coderidge)』のサポートを活用しましょう。
▼「自分のスキルが活かせる内定直結インターンを探したい…」
『コードリッジ(coderidge)』は、インターンに繋がる”無料”WEBエンジニア養成プログラミング!
まずはLINEで詳しく話を聞いてみる!登録はこちらから!
まとめ
生成AIを活用する上で、プロンプトの設計力は成果を大きく左右します。目的・条件・ターゲットを明確にし、適切な言葉で伝えることが、AIから質の高い出力を得るための鍵です。
生成AIのプロンプトの書き方のコツや注意点を事前に確認しておくことで、質の高い文章をスムーズに生み出すことができるでしょう。
加えて、シーンに応じた使い方を押さえておけば、業務や学習への応用もぐっと広がります。生成AIのプロンプトが初めての方は、慣れていない分、抵抗もあり最初は難しいと感じる方が多いでしょう。
しかし、プロンプトエンジニアリングは、今後さらに重要になるスキルです。しっかりと習得し、生成AIを“使いこなす側”に立ちましょう。
▼「自分のスキルが活かせる内定直結インターンを探したい…」
『コードリッジ(coderidge)』は、インターンに繋がる”無料”WEBエンジニア養成プログラミング!
まずはLINEで詳しく話を聞いてみる!登録はこちらから!
大学からプログラミングを始めるなら、
コードリッジ!
空き時間に完全無料でエンジニアに。
まずはLINE登録!
この記事を読んだあなたにおすすめ
記事を検索
まずはLINE登録!体験講座情報も!
LINE登録へ