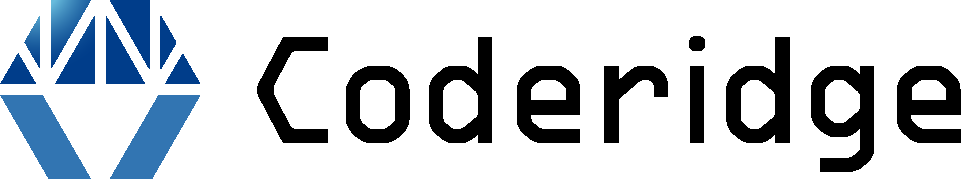「理系の学生って、いつからインターンシップに参加すべき?」「研究が忙しくて、インターンシップに行けるのか不安…」
そんな疑問や悩みを抱えている理系学生の方も多いのではないでしょうか。
実は、理系学生向けのインターンシップは、専門性や研究力を活かせるチャンスが豊富にあります。
理系の知識やスキルが必要とされる分野では、企業側も学生に対して高い期待をもっており、早期から参加しておくことで選考時に有利に働く可能性が高まるでしょう。
本記事では、理系学生ならではのインターンシップの特徴、参加時期や企業数、行かない理由、参加ステップなどをわかりやすく解説します。
将来の就職やキャリア形成を見据えて、自分に合ったインターンシップ選びの参考にしてください。
▼「自分のスキルが活かせる内定直結インターンを探したい…」
『コードリッジ(coderidge)』は、インターンに繋がる”無料”WEBエンジニア養成プログラミング!
まずはLINEで詳しく話を聞いてみる!登録はこちらから!
理系学生のインターンシップの特徴3つ
理系学生のインターンシップには、文系学生とは異なる特徴がいくつかあります。
特に、企業側のニーズや選考ルート、インターンシップで求められるスキルなどに違いがあるため、理系ならではの視点で情報収集・準備を進めることが大切です。
ここでは、理系特有の3つの特徴について詳しく紹介します。
- 理系学生の需要は高まってきている
- 理系学生限定のインターンシップがある
- 理系学生用の推薦枠を設けているものもある
理系学生の需要は高まってきている
理系人材に対する企業のニーズは年々高まっています。
特にIT、製造、医薬、化学、インフラ、エネルギーなどの分野では、高度な技術や専門知識を持った人材の確保が急務となっており、理系学生に向けたインターンシップも拡大傾向にあります。
この背景には、DX(デジタルトランスフォーメーション)やAIの普及により、理論だけでなく実装スキルも持ち合わせた学生を早期に囲い込もうとする企業の動きがあるのです。
とくに修士課程の学生は、研究成果や論文などを通じて技術的なポテンシャルを評価されることが多く、企業側の評価も高くなりがちです。
そのため、理系学生がインターンシップに参加することは、自分の専門性を活かす場を見つけると同時に、企業とのマッチングを図る絶好のチャンスとなります。
業界を横断してニーズが高まる今こそ、積極的に参加して可能性を広げましょう。
理系学生限定のインターンシップがある
理系学生のみを対象にした「理系限定インターンシップ」は、多くの企業で実施されています。
これらのインターンシップは、専門的な知識やスキルを持った学生に焦点を当てた設計になっており、実験、設計、開発、データ分析、システム構築などの実務に近い体験ができることが特徴です。
たとえば、製薬企業でのインターンシップでは、新薬の開発プロセスや臨床試験の設計、化合物分析などが含まれることもあり、大学の研究内容と直結した経験が積めます。
エンジニア職向けには、PythonやC++を用いたプログラミング課題、アルゴリズム構築、センサーデータの処理などをおこなう実践型インターンシップも増えています。
文系学生がいない環境だからこそ、企業側も技術的な深い話ができ、学生の本質的な理解度や応用力を評価しやすくなるのです。
自分の学びをそのまま活かしたいと考える理系学生にとっては、専門性を伸ばす絶好の場です。
理系学生用の推薦枠を設けているものもある
一部のインターンシップでは、大学経由での「推薦枠」が設けられている場合があります。
これは特に研究室単位で企業とつながりが深い理系学部でよく見られるケースで、教授や研究指導教員からの推薦があれば、通常の選考フローよりも優遇されることがあります。
この推薦枠の強みは、選考に通過しやすくなるだけでなく、実務内容がより学生の研究内容に合ったものになるケースが多い点です。
企業側も、大学と連携したインターンシップを通じて、即戦力候補を育てたいと考えており、推薦者に対する期待値も高く設定されています。
推薦があることで責任も生まれますが、その分、現場からの指導も丁寧で、インターンシップ終了後にリクルーターや特別選考につながる可能性も十分にあります。
研究室との関係性や過去の実績を確認し、利用できる推薦制度があれば積極的に活用しましょう。
理系学生のインターンシップはいつから行くべき?
インターンシップに参加する時期は、就職活動の進め方や学業の状況によって変わりますが、理系学生は特に「研究」との両立が重要なポイントになります。
3年生の夏におこなわれるサマーインターンシップが主流ですが、最近では1〜2年生向けの早期プログラムも増加中です。
ここでは、理系学生がインターンシップを始める適切な時期について、それぞれの特徴やメリットを交えて解説します。
- 3年生のサマーインターンシップが参加しやすい
- 1~2年生も対象としたインターンシップへの早期参加もおすすめ
3年生のサマーインターンシップが参加しやすい
理系学生にとって最も一般的で参加しやすい時期が、大学3年生の夏におこなわれる「サマーインターンシップ」です。
就活本番の一年前というタイミングで、企業側も「早期選考候補」として優秀な学生と出会う場として位置づけていることが多く、実質的な選考の一環ともいえます。
この時期のインターンシップは、内容が本格的なものも多く、実際の業務を体験できたり、社員と共同でプロジェクトを進める形式もあります。
技術系の職種では、開発業務、システム設計、研究補助などに参加でき、企業のカルチャーやチームの雰囲気もリアルに体感可能です。
また、同時期に複数社のインターンシップが開催されるため、比較しながら志望企業を絞ることもできます。
多くの学生がこのタイミングでインターンシップに参加するため、情報交換や仲間づくりにもつながり、就活準備のスタートダッシュとして最適な時期です。
1~2年生も対象としたインターンシップへの早期参加もおすすめ
近年では、1〜2年生を対象としたインターンシップも増えており、早期から社会経験を積むことの重要性が高まっています。
理系学生にとっても、早い段階で業界や職種のリアルを知っておくことは、将来の研究テーマや進路選択にも役立つ情報になります。
たとえば、短期のオープンカンパニー形式で「企業の説明+軽いワーク」をおこなうプログラムや、実験補助、工場見学、システム開発体験など、実務の導入として設計されたプログラムが多く、参加のハードルも低めです。
また、早い段階で企業と接点をもつことで、後の本格的なインターンシップや選考で名前を覚えてもらいやすくなり、将来的なアドバンテージにもつながります。
1〜2年生のうちに一歩踏み出しておくことで、就活が始まる頃には周囲と大きな差をつけられる可能性が高まります。
理系学生のインターンシップは何社行くべき?
理系学生がインターンシップに参加する企業数は、目的や時期によって異なりますが、最低でも2〜3社、可能であれば5社前後の参加がおすすめです。
複数社に参加することで、業界や職種の比較ができ、自分に合う働き方や企業文化を見極める材料になります。
特に理系の職種は専門性が高いため、「同じエンジニア職でも企業によって業務内容や使用技術がまったく異なる」というケースが少なくありません。
複数社での経験を通して、自分がどの環境に適しているかを明確にすることができます。
また、研究が忙しい場合は、短期と長期をバランスよく組み合わせることもひとつの手です。
夏休みや春休みを活用して1day〜1週間の短期インターンシップに参加し、興味のある企業を絞ったうえで、後期に長期インターンシップへ進むと効率的に経験を積めます。
ただし、数をこなすことが目的ではありません。1社1社での学びを深め、履歴書や面接で語れるような体験にすることが何より重要です。
理系3年生でインターンシップに行かない人の理由3つ
インターンシップは理系学生にとって有益な経験ですが、実際には3年生の段階で参加していない人も一定数います。
その理由には個々の事情や進路の違いがあり、「行かない=不利」とは一概にいえません。
ここでは、インターンシップに行かない人たちの代表的な3つの理由を紹介します。
- 研究が忙しい人
- インターンシップ以外に取り組みたいことがある人
- 大学院へ進学予定の人
「行かなかった場合どうなるのか?」と不安に感じている方は、自分の状況と照らし合わせて参考にしてみてください。
研究が忙しい人
理系学生の3年生にとって、研究活動は学業の中心であり、時間も体力も大きく消耗するものです。
特に研究室に配属されたばかりの時期は、テーマの理解や実験の準備などで手一杯になり、インターンシップのための時間を確保することが難しいという声が多く聞かれます。
加えて、教授や先輩から「研究最優先」の姿勢を求められることもあり、インターンシップ参加が後回しになるケースも少なくありません。
しかし、研究に真摯に取り組んでいること自体は十分なアピール材料になります。
就活時には「研究が忙しかったため参加しなかったが、その分、学会発表や論文執筆に注力していた」と説明できれば問題ありません。
重要なのは、何を優先し、どう成果につなげたかを語れることです。
インターンシップ以外に取り組みたいことがある人
インターンシップ以外にも、学生生活で力を入れたいことがある人もいます。
たとえば、留学、資格取得、学生団体の活動、ハッカソン参加、プログラミングの自主学習など、自らの目標に沿って別の挑戦を選んでいるケースです。
特に理系学生の場合、インターンシップでは得られない実践スキルや実績を別の形で積むことも多く、それが将来的に職種選びや自己PRにつながることもあります。
むしろ、「目的を持って主体的に行動していた」という事実が、選考時に高く評価される場合もあるのです。
大切なのは、インターンシップに参加しなかった理由が明確であり、ほかの経験をどのように就活やキャリアに結びつけるかを説明できることです。
ひとつの型にとらわれず、自分らしい選択ができていれば問題ありません。
大学院へ進学予定の人
大学院進学を前提にしている理系学生にとって、学部3年生の段階でインターンシップに参加する必要性を感じにくいことがあります。
「まだ就活は先だから」「まずは進学試験対策に集中したい」といった理由から、インターンシップを見送る選択をする人は少なくありません。
実際、研究職を志望している学生や、専門性をさらに深めたい学生にとっては、大学院での活動が最大のアピール材料となるため、無理にインターンシップに行く必要はない場合もあります。
ただし、進学後に企業との関係性を築くためにも、M1(修士1年)でのインターンシップ参加は強くおすすめします。
企業側も修士学生に対する期待が高いため、選考直結型のインターンシップが多く開催されているのです。
学部時代に行かなくても、進学後に目的意識を持って参加すれば十分に挽回可能です。
理系学生のインターンシップへの参加方法5ステップ
インターンシップに参加するためには、ただ応募するだけでなく、事前の準備が結果を大きく左右します。
特に理系インターンシップは、選考にテストや面接があるケースも多く、段階的な対策が必要です。
ここでは、理系学生が効率よくインターンシップを探し、合格するまでの5ステップについて、わかりやすく解説します。
- 自己分析
- 業界研究・企業研究
- 業界研究・企業研究
- インターンシップの試験対策
- インターンシップへの申し込み・選考
自己分析
インターンシップ選びにおいて最初に取り組むべきは、自分の価値観や興味、将来像を明確にする自己分析です。
理系学生の場合、「なぜ自分はこの学科を選んだのか」「どんな分野で研究しているのか」「研究や実験で何にやりがいを感じたか」など、学業とのつながりも振り返りながら分析すると効果的です。
また、大学の講義や実験、チーム活動、趣味などを通じて「得意なこと」「苦手なこと」「成長できた経験」を整理することで、自分に合った業種や職種が見えてきます。
自己分析は、インターンシップ選考時のエントリーシートや面接で「志望動機」や「自己PR」を語るうえでも必須の土台になります。
時間をかけて丁寧に言語化することで、将来のキャリア選択にも役立つ指針が得られるでしょう。
業界研究・企業研究
自己分析ができたら、次は業界・企業研究に進みます。
理系学生にとっては、自分の専攻がどのような業界で活かせるかを調べるところからスタートしましょう。たとえば、化学系なら製薬・素材メーカー、情報系ならIT・通信、機械系なら自動車やロボティクスなど、多様な分野が広がっています。
業界研究では、仕事内容や将来性、働き方などを比較することが大切です。
一方で企業研究は、「その企業ならではの強み」や「どんな人が働いているか」「育成制度の有無」など、具体的な情報を掘り下げて理解しましょう。
インターンシップの目的は「体験」ですが、企業側も選考の一環として見ているため、事前に企業研究をおこなっておくと志望度の高さが伝わります。
OB・OG訪問や説明会も活用すると、よりリアルな情報が得られます。
インターンシップの情報収集
インターンシップ情報を収集するには、就職情報サイト(マイナビ、リクナビなど)や大学のキャリアセンター、SNS、OB・OGの口コミなどを活用すると効果的です。
理系向けの専門サービスや学部専用掲示板もチェックすると、専門性の高い案件が見つかることがあります。
特に見逃してはいけないのが、大学経由の募集情報や推薦型インターンシップです。
研究室単位で募集があるケースや、教授推薦が必要な案件もあるため、定期的に指導教員やキャリア支援室に確認しましょう。
また、開催時期や選考スケジュールも企業によって異なるため、スプレッドシートなどで一覧化して管理すると応募漏れを防げます。
人気企業や技術職インターンシップは早期募集が多いため、早めの情報収集がカギになります。
インターンシップの試験対策
理系インターンでは、エントリー時にWebテストやプログラミング課題、技術筆記試験などが課されるケースもあります。
特にエンジニア系や研究開発系のインターンでは、基本的な数学力、物理・化学の知識、ロジカルシンキング能力が求められることが多いため、対策を怠らないようにしましょう。
一般的なSPIや玉手箱などの適性検査も出題されることがあるため、市販の問題集で事前に形式に慣れておくと安心です。
また、コーディング課題がある場合は、AtCoderやLeetCodeなどで腕試ししておくのも効果的です。
技術試験に加えて、自己PRや志望動機の準備も並行して行う必要があります。
試験対策を早めに始めることで、インターン直前に焦ることなく、余裕を持って応募できるようになります。
インターンシップへの申し込み・選考
準備が整ったら、いよいよインターンシップへの申し込みと選考です。
多くの企業ではエントリーシート(ES)とWebテストをもとに一次選考がおこなわれ、通過すれば面接や課題提出に進む流れとなります。
応募時には「志望動機」「研究内容」「学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)」など、明確に伝えることが求められます。
企業によっては、志望職種に沿った課題提出やチーム面接を実施するケースもあるでしょう。
提出期限や面接日程の管理も重要になるため、複数社を受ける際はスケジュールをしっかり組み立てましょう。
また、エントリー後は選考中の連絡対応や書類提出もスムーズにおこなえるように、メールの確認をこまめにする習慣も大切です。
最後まで丁寧な対応を心がけることで、企業側に好印象を与えることができます。
『コードリッジ(coderidge)』なら就活に必要なスキルが身につく
「インターンシップに参加したいけど、専門スキルに自信がない…」「せっかく行くなら、就職に直結する経験がしたい」
そんな理系学生におすすめなのが、『コードリッジ(coderidge)』です。
『コードリッジ』は、エンジニアを目指す理系学生と、即戦力を求める企業をマッチングする就活支援サービスです。
特長は、現役エンジニアによる学習サポートと、実務を想定した研修プログラムにあります。
未経験者でも、プログラミングや開発フローの基礎から実践的な内容まで段階的に学べるため、企業の求めるスキルを効率的に身につけることができます。
また、学習を終えた後は、そのスキルを活かせる企業とのインターンシップ・マッチングがおこなわれ、参加先選びで迷うこともありません。
企業との距離が近く、現場で求められるリアルな経験が得られるため、自信を持って本選考に挑める力がつきます。
「将来はエンジニアとして活躍したい」「就活に強い経験を積みたい」そんな理系学生にとって、『コードリッジ(coderidge)』は最適な一歩となるでしょう。
▼「自分のスキルが活かせる内定直結インターンを探したい…」
『コードリッジ(coderidge)』は、インターンに繋がる”無料”WEBエンジニア養成プログラミング!
まずはLINEで詳しく話を聞いてみる!登録はこちらから!
まとめ
理系学生にとって、インターンシップは自分の専門性や将来のキャリアに直結する貴重な体験の場です。
専門スキルを活かせる職場を見つけるチャンスであり、企業側も技術系人材に高い期待を寄せています。
本記事では、理系インターンシップの特徴や参加時期、必要な企業数、参加しない理由、参加までのステップなどを詳しく解説しました。
特に、「研究が忙しい」「進学予定」などの事情があっても、自分なりに軸を持って行動していれば決して不利にはなりません。
また、エンジニア志望の学生には、スキルの習得から企業マッチングまで一貫して支援してくれる『コードリッジ(coderidge)』の活用もおすすめです。
未経験からでも実務に近いスキルを身につけ、成長できる環境が整っています。
自分に合った道を見つけるためにも、早めの情報収集と準備を心がけ、理系の強みを活かせるインターンシップ先を見つけていきましょう。
▼「自分のスキルが活かせる内定直結インターンを探したい…」
『コードリッジ(coderidge)』は、インターンに繋がる”無料”WEBエンジニア養成プログラミング!
まずはLINEで詳しく話を聞いてみる!登録はこちらから!
大学からプログラミングを始めるなら、
コードリッジ!
空き時間に完全無料でエンジニアに。
まずはLINE登録!
この記事を読んだあなたにおすすめ
記事を検索
まずはLINE登録!体験講座情報も!
LINE登録へ